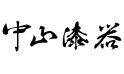心くすぐる透色の美
飛騨春慶
HIDA SHUNKEI

歴史
STORY
400年の歴史が息づく
伝統的工芸品
Traditional Crafts with
400 Years of History
飛騨高山を代表する伝統的工芸品、飛騨春慶。自然な木目が持つ素朴な美しさを活かしたこの漆器の始まりは400年前、江戸時代初期の慶長年間にまで遡ります。寺社仏閣の造営工事中に見つけた美しい椹材で透漆の盆を作り、皇族や幕府へ献上したことから、その歴史は始まったのです。

自然林に恵まれた土地
職人の魂
Blessed with Natural Forests,
Craftsmen's Spirit.
飛騨高山は古来より自然林に恵まれ、木材を使った様々な工業が発展してきました。木地の美しさを際立たせた飛騨春慶は、そんな豊かな自然と、匠たちの洗練された技、感性によって育まれてきたものなのです。

琥珀色に輝く自然のままの木目
Natural Wood Grain Shining in Amber.
飛騨の職人たちは皆手作業で一つひとつの製品を仕上げています。決して、芸術品を作っているわけではありません。飛騨の人々の真面目な気質が息づく器は、生活用品として日常の中でこそ輝きます。
職人
ARTISAN

Relying Solely on Senses.
400 Years of Woodworking
Craftsmanship and Tradition.
感覚だけが頼り
400年続く木地師の技と伝統
作業場に響き渡る木を削る音。
匠がノミを当てると木の板がお盆へと形を変えていきます。江戸時代より飛騨春慶は「刃物を切らして綺麗に仕上げる」と言われ、少しでも傷がつくと商品にはなりません。飛騨春慶が400年以上残ってきたのは木地師が切磋琢磨し、腕を磨いてきた結果です。

Lacquer Harvested Through
the Hands of Artisans.
漆の採取も
塗師の手作業
時の城主も愛でた薄黄色の透漆で塗り上げる飛騨春慶。生漆を自らの手でクロメた(精製した)春慶漆を塗り上げることで製品として仕上がります。
日常
DAYS
塗り物のある
生活
Living with Shunkei Lacquerware


食器棚に並んでいるだけで
心が躍る日常。
お菓子を置くと
さらに良い気分。


伝統と格式は少しだけ重い。
使ってみると
懐かしくて新しい。

あっ
日常の風景に
すんなり溶け込む。



新着
NEWS
- 2024.01.28
- ホームページリニューアルしました。